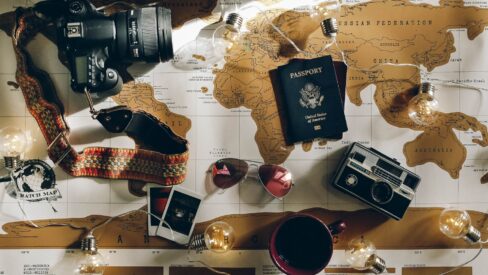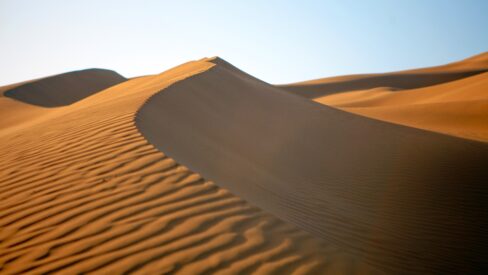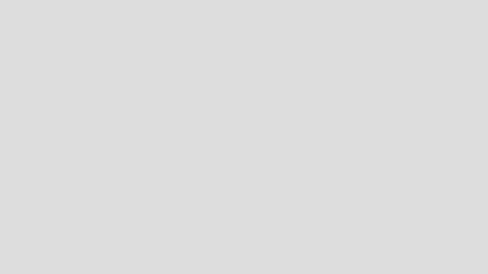【音声ガイド】京都嵐山の絶景街歩き
https://jp.pokke.in/wp-content/uploads/2021/07/06_01.mp3






このツアーでは京都の東に位置する山紫水明の地、嵐山を巡ります。
嵐山は1000年以上前から、京都貴族たちの別荘が並ぶ景勝地でした。
観光地化された京都中心部と比べて、当時の面影をいまなお強く残しています。
かつて京の貴族たちがこよなく愛した日本の原風景をたどってみましょう。
音声ガイドツアーの詳細
| タイトル | 京都嵐山の絶景街歩き |
|---|---|
| 場所 | 京都嵐山 |
| 体験の目安時間 | 約18分 |
| 利用方法 | 音声ガイドアプリPokkeをダウンロードして、いつでもお好きなタイミングでスタートできます。 ◆アプリのダウンロードはこちら iPhone / Android |